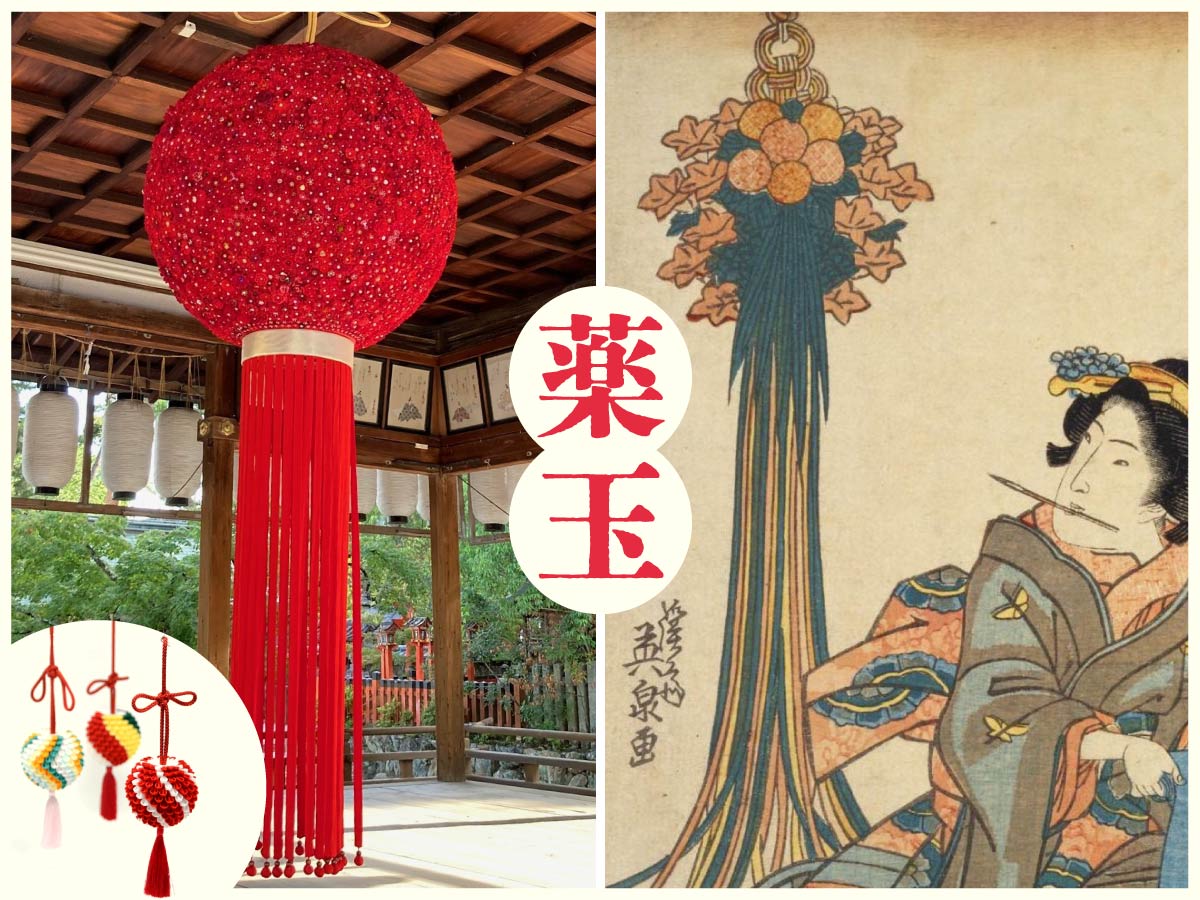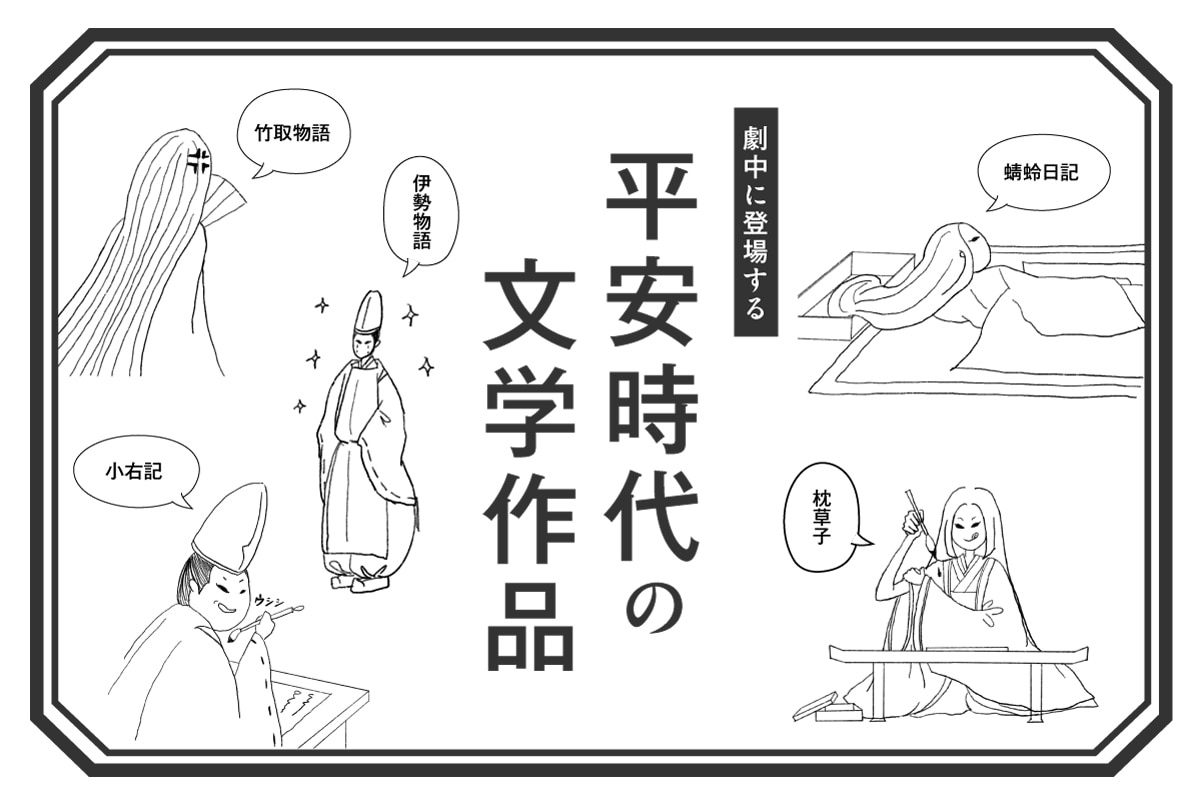平安時代、色とりどりの美しい十二単(じゅうにひとえ)を身にまとい、帝や中宮、女御たちに仕えていた女房たち。彼女たちが着ていた十二単とは、一体どんな衣裳なのでしょうか。今回は気になる女房たちの装束について紐解いていきます。
平安時代の衣裳といえば「十二単」

平安時代の衣裳というと一番に思い浮かべるのが十二単ではないでしょうか。
十二単は平安時代、貴人に仕える女房が着た正装。何枚もの袿(うちき)を重ね、後ろに裳(も:袴の上に腰部の後方だけにまとった布)を付け、唐衣(からぎぬ:一番上に羽織るもの)を着た装束をいいます。
400年続いた平安時代の中でも流行があり、現在イメージするようなスタイルになったのは藤原道長の姉・詮子が生んだ一条天皇の時代ともいわれています。まさに紫式部や清少納言が活躍した時代ですね。

十二単を着る順番は、まず白い「小袖」などを着て「長袴」を履きます。その上に「単(ひとえ)」を重ね、十二単の醍醐味である袿を5枚重ねた「五衣(いつぎぬ)」を着ます。
この五衣と次に着る豪華な「表着」の色の組み合わせを「重色目(かさねのいろめ)」といい、ここがセンスの見せどころ。
さらに「裳」を付け、上に「唐衣」を着たら完成です。
実は偉い人ほどラフな装い?!

画像提供:ACフォト
先ほど、十二単は女房が来た正装といいましたが、実は十二単は高貴な人が着るのではなく、お仕えしている人が着た装束なのです。
中宮や皇后など尊い身分の方は唐衣や裳を付けず、表着の上に少し丈が短いイラストのような小袿(こうちぎ)をゆったりと着てくつろぎ、その前に侍(はべ)る女房——例えば紫式部や清少納言などが豪華な十二単を着ました。
それゆえ十二単は「女房装束」とも呼ばれています。
清少納言が書いた『枕草子』にも、身分の高い人は唐衣と裳は付けないことが分かる記述があります。
それは関白・藤原道隆が積善寺で一切経の供養を催した時のこと。一条天皇の母・詮子、清少納言が仕えている中宮・定子、定子の母・貴子も列席しました(道隆にとって詮子は妹、定子は娘、貴子は妻)。
定子の桟敷に座った貴子は、中宮の母ということもあってか裳を付けた上に小袿を着ただけの略装だったのに対し、定子は唐衣と裳を着用した正装でした。それを見た道隆が「三位の君(貴子のこと)、中宮様の御裳をお脱がせなさい。中宮様こそ、この場の主君なのです」と涙したとあります。つまり妻は略礼装なのに対し、中宮様が正装をしていたことが申し訳なかったということですね。娘であっても中宮の方が偉いので、唐衣・裳は身に付けずともよいということなのです。
たなびく裳にオリジナリティをこめて

というわけで、高貴な方の前に出る時、唐衣と裳を付けることは重要でした。
女房たちは、裳のデザインに思い入れがあったようで、素材にこだわったり、刺繍や螺鈿(らでん)をほどこしました。写真でも奥の女房の裳は紅色の裾濃(すそご=グラデーション)ですし、手前の女房は摺(すり)を施しています。
お雛様などを見ると裳は唐衣の上から付けていますが、平安時代は写真のように唐衣の下にしていました。一見するとジャケットを着ているような感じですね。

紫式部が書いた『紫式部日記』には女房ファッションの記載が多く登場しますが、中でも紫式部が仕えた中宮・彰子の出産にあたっての女房らの装い、特に唐衣と裳について、こと細かく描写しています。
当時、出産の時から産後しばらくは、写真のように産室の御帳台や几帳、畳の縁から女房の衣装まで全て清浄な白色に改めるのですが、そのような中でも女房たちはファッションセンスをキラリと見せるのです。
ご紹介するのは、産後の「御湯殿の儀(産湯とは別に儀式として行わう入浴行事)」での装いです。

まず女房の一人である宮の内侍の衣裳は
「唐衣は松ぼっくりの模様、裳は海賦(かいふ)を織り出して、白一色とはいえ(定番の)大海の摺り模様(おおうみのすりもよう)をかたどっている。大腰と引腰は羅で作られていて、唐草が刺繍してある」もの。
別の女房・小少将は
「大腰には秋の草むらや蝶、鳥などを銀細工で作り、キラキラさせている。(宮の内侍のような)織物の裳は身分制度があって、意のままに着ることはできないので、大腰と引腰の部分だけをいつもと違えている」とあります。(画像はイメージ)
白一色でも飛び切りのおしゃれをしている様子が伺えますね。(画像はイメージ)

ここに出てくる定番の“大海の摺り模様の裳”とは、このような感じでしょうか。
大海と海賦は同じことで、大波や貝、砂浜などの海辺の風物や景色を文様化したもの。清少納言も『枕草子』で「裳は大海」と記しています。このデザインさえ取り入れていたら大丈夫! という宮中のトレンドだったのでしょうか。
加えて、今回お話を伺った鳥居本先生は「海に憧れがあったのかもしれませんね」とおっしゃっていました。都は海から遠かったので、海を見たことがある人は、ほとんどいらっしゃらなかったのでしょうね。
季節感が重要な「重色目」

さて、先述の通り、十二単の醍醐味の一つに「重色目(かさねのいろめ)」があります。
重色目とは、衣を重ねた時の襟元や袖口から見えるグラデーションや色の組み合わせのこと。この重色目をステキに着こなすこと、シチュエーションで色を選ぶことでセンスを表したようです。
当時、色はたくさんあり、植物の山吹のように赤味がかった濃い黄色は「山吹」、黄橙(おうとう)色は「朽葉色(くちばいろ)」、赤身のある紫色は「杜若(かきつばた)」、ピンクのような淡い紅色は「紅梅」などと美しい名前が付いていました。

その色をいくつか組み合わせたのが重色目です。それぞれに「梅がさね」(写真)「山吹がさね」「紅葉がさね」などと花や季節の名前が付き、着る時期が決まっていました。その時期を過ぎて着ることは恥ずかしいことですが、季節の先取りはOKだったようです。
ですから「梅がさね」は梅が咲く少し前から盛りの11〜2月に着るのが決まりだったようです。

好き嫌いでコーディネートを選ぶことはできないのですね。とはいえ、当時は「この季節にこのコーディネートがおしゃれ!」などと書かれたファッション誌はありませんし、色の組み合わせを描いた本もありません。
そこで何を着たらいいのか悩んだ時、庭の花を見たり、これから咲く花を考えると自然に色目の正解が分かるように、重色目には花や自然の名前が付いているのではないか…と考えられるそうです。

もう一つ心配なのは、こうも色の指定が細かいと、さまざまな色の袿が必要なのではないかということです。が、心配はご無用。実は紅や萌黄など同じ色が幾度も使われているんです。さらに、同じ色合いでも秋になると名前が変わったりするそうですよ。
そして袿はどれも同じ大きさで仕立てるので、組み合わせは自由。肩に沿う様に着付けることで自然と衣がずれ、美しい色目が作られるのだそうです(もちろん襟の幅をどれだけ出すかなどのコツはあったでしょうけれど)。
長い黒髪は美人の条件

衣裳が決まったら最後はヘアスタイルです。
平安時代のヘアスタイルは結い上げず、下ろしたままが基本。しかも女性は人前で顔を見せることがなかったので、長い黒髪が美人の条件でした。清少納言も羨ましくみえるものとして、「髪が長く、毛筋が整っていて、額髪(ひたいがみ)の切り揃えたところがキレイに見える人」と記しています。
しかも長ければ長い方が良いとされ、身長より30㎝も長い女性もいました。しかし、いかに奥ゆかしいお姫様でも時には長い髪が邪魔になったのでしょうね。中には食事中、髪を持つ役目の人がいた場合もあったそうですよ。
また、女房などは忙しいと「耳挟み」といって耳に掛けたりもしたのだとか。ですが頻繁に「耳挟み」をしていると行儀が悪いといわれてしまったんですって。

また、髪の少ない人は髢(かもじ)と呼ばれる付け毛をしました。今でいうエクステですね。『紫式部日記』では、「色白にほんのり紅が差しとても端正な顔をした式部と言う人は、髪も美しいのですが長くはないので(中宮・彰子の)御前にお仕えする時は付け髪を足している」と書いています。
いかがでしたでしょうか。平安時代の女性たちも、現代の私たちと変わらず、おしゃれには敏感で身だしなみに気を遣っていたことがわかります。
現在放送中の大河ドラマでも、色鮮やかな装束が見られるので、ぜひ、当時の衣装にも注目して見てみてくださいね。
お話を伺った方
鳥居本幸代(とりいもとゆきよ)先生

京都生まれ。同志社女子大学卒業。京都女子大学大学院修了。家政学修士。専門は平安朝服飾文化史および、平安朝を中心とした衣食住に関わる生活文化史。神戸女子短期大学助教授、姫路短期大学助教授、姫路工業大学助教授を経て、2003年より京都ノートルダム女子大学教授。2018年定年退職。現在は京都ノートルダム女子大学名誉教授。著書に『平安朝のファッション文化』『雅楽-時空を超えた遙かな調べ-』『千年の都 平安京のくらし』『紫式部と清少納言が語る平安女子のくらし』(いずれも春秋社)など多数。
■■撮影協力■■
■■参考文献 ■■
『紫式部と清少納言が語る平安女子のくらし』(春秋社)
『別冊太陽 有職故実の世界』(平凡社)
『紫式部日記 現代語訳付き』(角川ソフィア文庫)
『源氏物語 付現代語訳』 (角川文庫)
『あたらしい平安文化の教科書』(翔泳社)